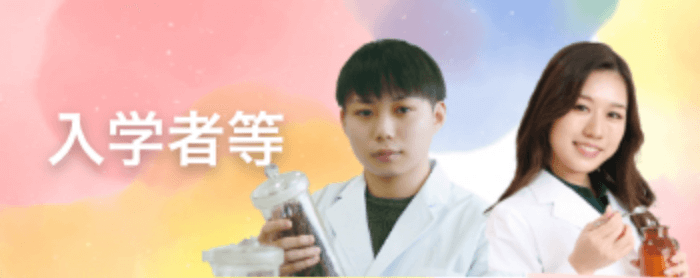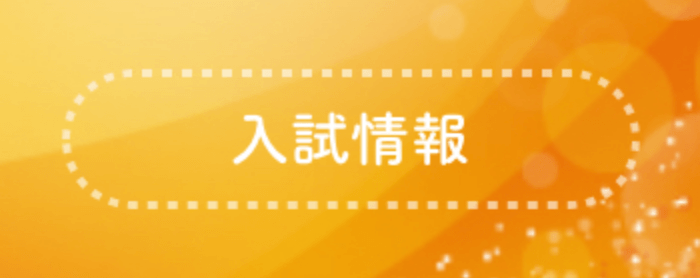学部・学科・大学院大学院 薬学研究科[薬学専攻(博士課程)]
- 学部・学科・大学院
- 大学院
1)研究科長メッセージ
大学院薬学研究科のご紹介
研究科長(教授)中原 広道
第一薬科大学は、建学の精神である「個性の伸展による人生練磨」を教育理念としています。この理念のもと、令和3年(2021)年度に大学院薬学研究科薬学専攻(博士課程)を設置しました。本学大学院は、今年で開設3年目を迎えました。この3年間、皆様のご支援のおかげで、着実に成長を続けてまいりました。
本大学は、漢方薬学を学部で専門的に学ぶことができる西日本で初めての大学であり、本学大学院では、特に漢方薬学研究に力を入れております。漢方薬学は、日本の伝統的医学の知恵に基づいた、自然由来の薬物療法のことです。近年、漢方薬の有効性が科学的に証明されつつあり、世界中で注目を集めています。
本学大学院では、漢方薬の研究開発、教育、普及に取り組んでおります。漢方薬の研究開発では、新しい漢方薬の開発や、既存の漢方薬の有効性・安全性の向上に取り組んでおります。教育では、漢方薬学の基礎知識から、臨床応用までを学ぶことができます。普及では、漢方薬に関する講演会やセミナーを開催し、一般の方々に漢方薬の知識を広めております。
本学大学院では、漢方薬学に興味のある方、漢方薬学を学びたいという方、漢方薬学で社会に貢献したい方を広く募集しております。
本学大学院は、漢方薬学研究の拠点として、社会に貢献することを目指しております。皆様のご支援をよろしくお願い申し上げます。
2)教育の目的
「薬」に関する深い専門的知識・技術を身につけ、基礎薬学及び臨床薬学に関する研究活動を自立して遂行し、新たな課題を見出して、それに取り組むことができる高度な研究能力を有するとともに、最新の研究機器と最先端技術を駆使して西洋薬及び「補完・代替医療」の中核となる漢方薬や伝統薬の作用機序を解明する研究を通して、「統合医療」を実践できる薬学教育者あるいは薬学研究者の育成を目的とする。
3)3つの方針(ポリシー)
-
学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)
本学薬学研究科薬学専攻博士課程は、所定の単位を修得し、博士論文が学位論文審査及び最終試験に合格した者に対し博士(薬学)の学位を授与する。
- 医療人としての責任感と倫理観をもって研究を遂行できる。
- 基礎薬学及び臨床薬学分野において、高度な専門的知識・技術を有している。
- 自ら問題を発見し独創的な発想に基づいてその解決を図り、自立して研究活動を行うことができる。
- 「統合医療」を理解し、地域社会や国際的視点から、医療と薬学の諸問題に対応できる。
-
教育課程編成・実施の方針(カリキュラム・ポリシー)
本学薬学研究科薬学専攻博士課程は、基礎薬学と臨床薬学の研究領域において、ディプロマ・ポリシーに則した人材を養成するため、以下のような方針に基づいて教育課程を編成・実施する。
- 研究を行うに必要な倫理観や国際的感覚、プレゼンテーション能力を醸成する。
- 地域社会のニーズに応えるために必要な幅広くかつ深い学識を修得する。
- 「統合医療」に適正に対応するための、より高度な専門的知識を修得する。
- 自ら問題を発見し、その解決を図ることができる研究能力を養成する。
- 各科目の学修成果の客観的評価については、シラバスに示した評価方法及び評価基準に基づき厳格に評価する。
-
入学者受入れの方針(アドミッション・ポリシー)
本学大学院薬学研究科薬学専攻博士課程は、建学の精神である「個性の伸展による人生錬磨」を基本理念とし、次のような学生を受け入れる。
- 薬学に関する基礎的学力と研究技術を身に付けている。
- 生命を尊重し他者を思いやる心と倫理観を持っている。
- 薬学分野に関心を持ち、自ら課題を発見し、それを解決するための研究を行う意欲がある。
- 高度な薬学分野の専門知識・技術を修得し、人々の健康維持・増進に貢献しようとする意欲がある。
4)学位論文に係る評価に当たっての基準
5)各種規程
6)指導教員、課題研究一覧
| 領域 | 分野 | 担当教員 | 課題 |
|---|---|---|---|
| 基礎薬学領域 | 薬品化学分野 | 教授 門口泰也 |
医薬品に代表される機能性物質の合成に有用な有機反応の開発 |
| 薬物解析学分野 | 教授 小松生明 |
難治性疼痛に対する新規治療薬の探索研究 | |
| 教授 田畠健治 |
熱生産に基づいたエネルギー代謝の制御 | ||
| 分析化学分野 | 教授 藤井清永 |
医学・薬学領域に有用な分析技術の開発とその応用に関する研究 | |
| 天然物化学分野 | 教授 長島史裕 |
医薬品創製を目指した天然医薬シーズの探索 | |
| 分子生物学分野 | 教授 炬口眞理子 |
造血器腫瘍治療におけるバイオマーカーの探索 | |
| 臨床薬学領域 | 衛生化学分野 | 教授 副田二三夫 |
QOL改善薬、特に排尿障害治療薬・予防薬の開発に関する研究 |
| 教授 藤井由希子 |
環境化学物質の分析化学的研究と健康影響評価 | ||
| 和漢薬物学分野 | 教授 森永紀 |
甘草の副作用、偽アルドステロン症の発症予測のための検査キットの開発 | |
| 薬品作用学分野 | 教授 有竹浩介 |
プロスタグランジンD合成酵素阻害薬の分子設計と新規抗炎症薬への応用研究 | |
| 薬物治療学分野 | 教授 小山進 |
脂肪-脳連関を軸とした食行動制御と肥満に関する研究 | |
| 准教授 山脇洋輔 |
グリア細胞活性化によるストレス脆弱性獲得機序に関する研究 | ||
| 臨床薬剤学分野 | 教授 有馬英俊 |
シクロデキストリン・サクランの医薬への応用と人工知能(AI)の利活用 | |
| 地域医療薬学 センター |
教授 窪田敏夫 |
地域における薬剤師の薬学的管理の有用性に関する研究 | |
| 教授 首藤英樹 |
医薬品適正使用の推進・実践を目指した医療薬学(育薬)研究 | ||
| 教授 大光正男 |
薬局における薬剤師介入による医療効果の向上に関する研究 | ||
| 薬剤設計学分野 | 教授 中原広道 |
新規人工調製肺サーファクタントの開発研究と経肺DDSへの応用展開 | |
| 生薬学分野 | 准教授 久保山友晴 |
難治性神経疾患の根本治療を目指す和漢薬研究 | |
| 薬学教育推進 センター |
教授 村山惠子 |
生体微量成分の代謝・制御に関する研究 |